
2025年6月14日(土)、京都大学 総合研究2号館にて、関西大学SCL養成講座修了生と京都大学SCD養成講座修了生による合同同窓会を開催いたしました。
本同窓会は、関西大学SCL・京都大学SCD両講座の枠を越えた修了生同士の交流の促進、そして修了後に培った知識や経験を共有し、あらたな学びと刺激を得る場となることを目的に開催したものです。
当日は、2018年度に実施された関大SCL第1期生から、2024年度の関大SCL第7期・京大SCD第1期修了生まで、幅広い期の修了生にご参加いただき、非常に活気ある交流の場となりました。
開催概要
日時:2025年6月14日(土)
会場:京都大学 総合研究2号館
プログラム
【オープニング】13:00-13:20
開会挨拶:蓮行(京都大学 特定准教授/SCL・SCDプログラムディレクター)
自己紹介ワーク(ファシリテーター:紙本明子氏)
【第一部】13:20-16:30
修了生による実践・活動・研究発表(口頭・ポスター)
【第二部】17:00-19:00
交流会
オープニング
冒頭では、SCL・SCDのプログラムディレクターである蓮行先生より、本会の趣旨についてご説明いただきました。
蓮行先生は、「分散知を集め、集合知へと高め合う」というSCL・SCDの共通理念に触れながら、講座を通じて得られた学びや実践が、それぞれのフィールドでアップデートされ、今回の同窓会を通じて再び交差・共有されることの意義について語られました。
続いて、ファシリテーターの紙本明子氏による自己紹介ワークを実施。
「名前」「修了期」「自分が思う“今/今日”の点数(あえて何の点数かは明示しない)」を一人ずつ発表し合う形式で、自己開示をしつつも心理的安全性が保たれた温かな場となり、参加者の距離がぐっと縮まりました。
第一部:修了生による発表
続く第一部では、修了生による口頭・ポスター発表が行われ、それぞれの実践や研究に基づいた多彩な発表内容が披露されました。
口頭発表
阿部 翔吾さん(SCD1期)
教室全体を活用したダイナミックなコミュニケーションゲームを通じて、即興的な協働と対話のプロセスを体験する実践を行いました。
細部までルールが決められていない状況で、参加者同士が自発的に動き、試行錯誤しながらゴールを目指すことで、「バラバラの正解をすり合わせる」経験が得られました。
発表後の質疑応答では、教育現場での応用可能性や、異なる年齢層・場面での展開についても議論が広がり、実践の広がりと深まりの両面に可能性を感じさせる内容でした。

小林 誠さん(SCL2期)
サイエンスコミュニケーションの観点から、「伝える」と「伝わる」の違いを考えるワークを実施されました。
2冊の雑誌に使われた猫の写真を比較するというシンプルな題材をもとに、それぞれの捉え方や感じ方がいかに異なるかを参加者同士で確認し合い、自分の常識や前提が必ずしも他者と共有されているわけではないことを実感する機会となりました。
このワークは、文化的背景や個人の価値観によって「正解」が変わるというサイエンスコミュニケーションの核心を体感的に学べる内容であり、対話における「焦点合わせ」の重要性を再認識する時間となりました。

「ロジマジ」制作委員会(SCD1期)
論理的思考(ロジ)と感情的表現(マジ)を融合させた対話トレーニングゲーム『ロジマジ』の実践を行いました。
プレゼンテーションの中で「ロジ技(証拠・数字)」と「マジ技(表情・共感)」のバランスを取ることが求められ、参加者は「感情をどのように言語化・可視化するか」に意識を向けながらプレゼンを作り上げました。
また、「表情で意見を伝える」などの制約があることで、普段意識していなかった身体的・非言語的な表現の効果にも気づかされ、論理と感性の両輪がプレゼンテーションの説得力を支えることを実感する貴重な体験となりました。
※『ロジマジ』は、SCD1期生の修了研究にて開発・作成された対話トレーニングゲームです。

橋本 賢さん(SCL3期・SCD1期)
「難病を“自分ごと”としてとらえる」をテーマに、ゲーム形式のワークショップ開発に取り組まれた実践を発表いただきました。
症状や通院の頻度、就業状況などを示すカードを使って、当事者の状況を理解し、就労環境をどう整えるかを参加者自身がチームで考えるプロセスを体験。
ワークの目的は、知識のインプットにとどまらず、参加後も当事者との関係性が継続するような「出会い」の創出にあり、「当事者の声を取り入れたゲーム設計」「会社経営シミュレーションとの組み合わせ」「演劇的手法の活用」といった多様なアイデアが寄せられました。
社会課題を可視化し、かつ“当事者不在”にしない実践の設計がいかに可能かという点で、多くの示唆を与える発表でした。

ポスター発表
- 谷井 由実子さん(SCL1期・SCD1期):学習塾でのDE&I実践に関する報告
- 辻岡 啓司さん(SCD1期):SCD養成講座の学びを人間中心設計の視点で振り返る
- 澤山 美絵さん(SCD1期):「ロジマジ」についての解説
各ポスターには多くの参加者が集まり、実践に基づいた熱心な議論が交わされました。
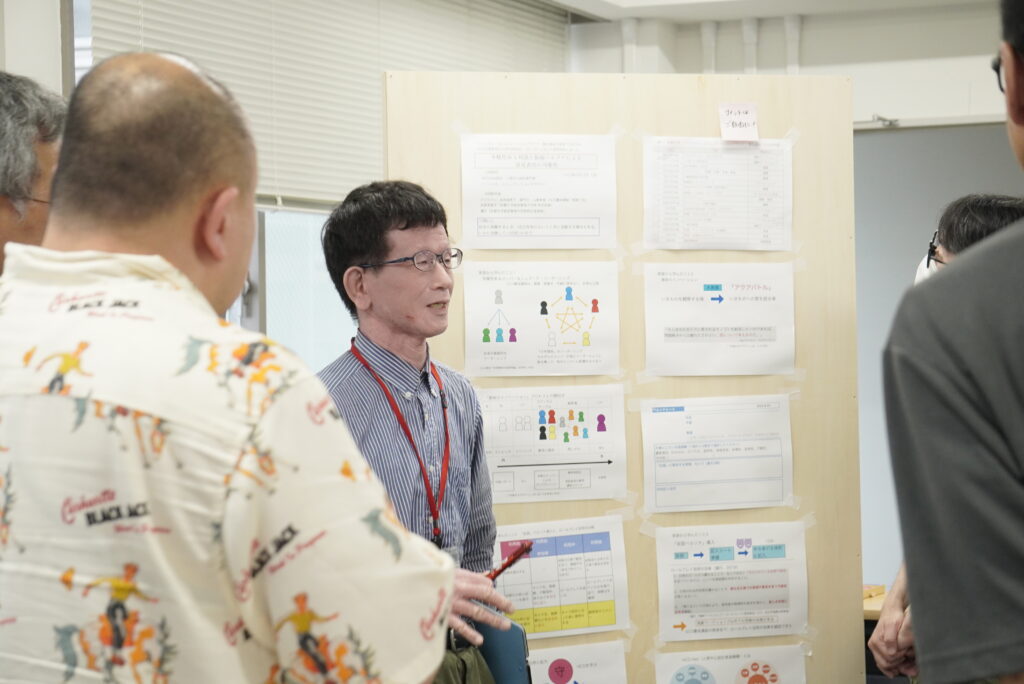


第二部:交流会
夕方からは、軽食を囲みながらの交流会を実施。発表を通じて興味を持った方同士がさらに話を深めたり、期を越えた再会と新しい出会いに花が咲くひとときとなりました。SCLとSCDの修了生が世代や所属を越えてつながる貴重な機会となり、会場には笑顔と熱気が溢れていました。
まとめ
今回の合同同窓会は、修了生同士のあたたかな再会にとどまらず、各自が講座後に積み重ねてきた実践や探究を持ち寄り、「これから」の活動への新たなヒントや刺激を得る時間となりました。
また、SCL・SCD講座で重視されている「集合知の生成」というテーマが、まさにこの場においても体現されており、今後の各自の活動の土台となる“学び合いのネットワーク”が、今後ますます広がっていく可能性を感じることができました。
今後もこうした場を継続的に設け、修了生が実践と学びを共有し、支え合う関係性を育んでいければと思います。
ご参加いただいた皆さま、発表・登壇いただいた皆さま、そして同窓会実行委員の皆様、本当にありがとうございました。



コメントを残す